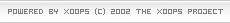| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| webadm | 投稿日時: 2008-10-9 11:06 |
Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3110 |
回路網解析と基本諸定理演習 さていよいよ上巻も残すところ三分の一に迫った。
さっさと終わって下巻に進みたいところ。 回路網理論を学ぶと、ちょっぴり電子回路理論を学ぶための基礎ができたような感じがする。 本屋で参考書をいろいろ見ると、電子回路の本でも最初に回路網理論の基礎だけはおさらいしている。電子回路の場合には、非線形デバイスが使われるので厳密には線形回路ではないのだが、限られた条件下では線形回路網理論が応用できる。ほとんどの市販の電子回路設計の参考書は読者が予めそうした基礎を学んでいることを暗黙の前提としているので、いきなり電気を勉強せずに電子回路を学ぼうとしても無理がある。やっとなんというか念願だった、トランジスタが複数接続された回路の解析のやり方が見えてきたように思える。途中休み休みだったとはいえ長い道のりだった。 もちろん電子回路解析や設計となると、これから学ぶことになる理論も知っていないと話にならない。また戻って勉強しないといけないことになるのでここはぐっとこらえて知識をつなげていこう。 最終的には電気の理論の本当の裏付けになっている電磁気学をマスターする必要があるが、それま下巻をマスターした後の楽しみとしよう。電磁気学も個人的に興味があるのは、最後の変動する電場と磁場の理論なのだけど、いきなりそれだけ理解するということは無理なはなしで、やはり基礎となる静電場や静磁場の理論から入っていく必要がある。その前にベクトルとテンソルに関する数学もおさらいする必要がある。学校で物理学の授業を受けた人であれば数学でベクトルとテンソルや波動方程式とかもやっているはずだが、普通はすっかり忘れてしまうだろう。実は電気でも重要な意味を持つのだが、それは学生の頃には教えてもらっていないか、忘れてしまったに違いない。 ざっと演習問題を眺めると、既に理論を学んだ時にやってしまった証明問題とかがあるので、それらはスキップすることにしよう。 |
| フラット表示 | 前のトピック | 次のトピック |
| 投稿するにはまず登録を | |