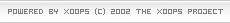| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | 下へ |
| 投稿者 | スレッド |
|---|---|
| webadm | 投稿日時: 2020-5-18 3:28 |
Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3110 |
VILAB Ravenscroft 275 PC音源購入 ふう、蒸し暑いね(´Д`;)
先日テレワークを開始するまでは、普段はデジタルピアノ音源用にデジタルピアノの傍においてVILABS Ravenscroft 275 piano音源を介して練習していたのですが。 テレワークで使用するVPNの接続にはワンタイムパスワードが必要とのことでAndroidかiOSの携帯が必要ということで、普段使っているガラケーは使えず、仕方なく自宅のiPadを急遽ワンタイムパスワード用に使うことに。 そしたらね、VPN接続開始時だけじゃなくて、その後数時間間隔で勝手に行われるrekeying(通信の暗号化キーを新しいものに変えて第三者が暗号化キーを解読しても使えないようにするため)時に再接続するのに必要になるのよね。 本来はrekeyingはVPNサーバーとクライアントで自動的に行われるものだけど、ワンタイムパスワードを無理やり導入したためか、rekeying時にもワンタイムパスワードが居る仕組みになっていて自動では対応できなく、接続は維持してもその後通信不能な状態になることが判明。 そのため、rekeying時に通信が不能になったら、強制的にVPNを切断して再度接続するのにワンタイムパスワードが必要ということでPCの傍に常に置いておかないといけないことに。 なのでデジタルピアノ音源は中古再生ノートPC(最初からSSD化してある)のMODARTT PIANOTEQのsteinway B 音源を使用していました。 Steinway B もいいけど、やっぱりタッチで音色が変わるRavenscroft 275音源が恋しくて、PC用のVILABS Ravenscroft 275音源を買うことに。 最初から買っておけばよかったけど、iOS版のUVI Ravenscroft 275 Pianoが気に入っていたので、それでいいかと思っていたのでした。 ここまで前置きが長かったね( ´Д`) 購入自身はアマゾンでポチっとしただけなので、たぶん沢山ある代理店のどかから購入しても同じだし、本家から購入しても同じだと思うけど、アマゾンの製品評価コメントにもあるように導入方法がわかりずらい。 買う前は、へえ、そんなに難しいのかな、たかがPC用のソフトなのに。 と半信半疑だったのですが、実際に自分で購入してみて、なるほどこれは頭おかしいわと思うぐらいわかりずらいものでした。 購入したベンダーからは日本語訳された導入手順書がPDFで添付されているけど、作成時期が古いのか最新のソフトのバージョンと細部が異なるので、これもまた導入を妨げる要因になります。 まず、これからVILABS Ravenscroft 275 音源を買おうと思っている人向けに、必要事項を書いておきます。 (1) iLOK公式サイトにユーザーアカウントを登録する(必須) (2) iLOK license managerアプリをPCにダウンロードしVILABS Ravenscroft 275を使用するPCにインストールする(必須) (3) VILABS公式サイトにユーザーアカウントを登録する(必須) (4) VILABS公式サイトからUVI Workstation をダウンロード&インストールする(他にVILABが対応するDAWソフトがインストールされていなければ使用するのに必須) (5) VILABS公式サイトで購入業者からメールで送られてくる製品シリアル番号を登録する (6) iLOK license manager を起動して、iLOK singin ボタンをクリックして自分のiLOK アカウントのユーザ名とパスワードを入力してログインする (7) iLOK licence managerで表示されるVILABSで登録した製品シリアル番号を現在のPC上でactivateする(ひとつの製品は同時期に3つのPC上でactivate可能、リアルタイム演奏用、DAWデスクトップPC用、屋外演奏用ノートPC等で同時使用が考慮されている) (8) VILABS公式サイトで登録したアカウントでログインし、Ravenscroft 275 ライブラリをダウンロードする (9) ダウンロードしたライブラリは圧縮されているので、解凍ソフト(RAR)を別途ダウンロード&インストールする (10) Ravenscroft 275 ライブラリを解凍して、UVI workstationのsoundbankディレクトリに展開する(場所はどこでもいいが、それ以外の場所だとUVI workstationで設定をそちらに変更する必要がある) (11) UVI workstationを起動して、展開されたRavenscroft 275音源をロードする (12) PCにMIDIキーボードを接続後にUVI workstationのFileメニューにあるAudio and MIDI settingメニューを開いて、MIDI settingを開いて、MIDI device rescanボタンを押して、A portのデバイス選択をクリックして認識されているMIDI keyboardを選択する これでMIDIキーボードを使用してリアルタイム演奏ができるようになります。 最低でも12ステップも手順がかかるとかありえないよね。 VILABSの他音源でTreuKeyがあるけど(Ravenscroft 275も同じ技術を使っているぽい)、魅力的だけどまた同じ苦労と時間をかける精神的余裕は今はない( ´Д`) 以降で詳しく各ステップを画像入りで説明しておくね。 詳細編 (1) iLOK公式サイトにユーザーアカウントを登録する(必須) VILABの製品は不正コピーを未然に防ぐために、iLOK社からライセンスを受けた技術を使用しています。 このためVILABSの製品を使用する際には、iLOK社に自分のアカウントを登録して自分以外の第三者が不正にコピーして利用できないようにする義務があります。 iLOK社は元来不正コピー防止技術の一環でUSBドングルを開発しそれを接続したPC上だけでラインセンスされたユーザーに商用ソフトウェアを使用可能にする技術を商品としていますが、USBドングル無しでも同社の専用ソフト(iLOK license maanager)をUSBドングルの代わりに商用ソフトを使用するPCに導入することが可能です。 VILABS社はおそらくiLOK社から各製品でその技術を使用するライセンスを得てロイヤリティを予め支払っているので、iLOK社からUSBドングルを買う必要はなく(買ってくれればiLOK社は二度美味しいけど)、iLOK license managerソフトを導入してそれをUSBドングルの代わりに使用するので十分です。 iLOK license managerは確かUVI Workstationをインストールする際にまだインストールされていない場合は確認画面が出てインストールするか尋ねられるので、その際にインストールしても問題ないかも。 iLOK公式ページ  公式ページトップの"Create Free Account"をクリックすると新規ユーザーアカウント登録ページになります。  英語だけど、必須欄を入力して利用条件を承諾するチェックボックスをチェック済にして"Create Account"をクリックすると、メールアドレス確認のためのメールが入力したメールアドレスに届くので、メールを受信してそのメールにある確認用のリンクを開く必要があります。 ((2) iLOK license managerアプリをPCにダウンロードしVILABS Ravenscroft 275を使用するPCにインストールする(必須) これは先にやってもいいですし、後でUVI Workstationをダウンロードしてインストール際にも併せて行えるのでその時でもいいです。 (3) VILAB公式サイトにユーザーアカウントを登録する(必須) 購入した代理店から送られてくる製品シリアル番号を使ってユーザー登録するために公式サイトでユーザーアカウントを作成する必要があります。 VILABS公式ページ  公式ページトップの左上の"ACCOUNT"をクリックすると出てくるサブメニューから"Sign Up"を選択すると新規ユーザー登録ページが表示されます。  英語だけど、必須入力欄は赤で囲った部分だけ。 何故かCompany IDとTax IDに*がついて必須になっているように見えるけど必須ではないぽい。 たぶんこのソフトを使用するのは楽曲制作を生業とする個人事業主か企業だと前提しているよね。もしかしたら住所とかも必要ないかも。 例によって利用条件を承諾した旨のチェックボックスをチェック済にして"CONTINUE"をクリックします。 これで登録が完了し、登録したメールアドレスにその旨のメールが届きます。iLOKのようにメール確認用のリンクではないですが、ログインページのリンクが張られているのでそこからログインページを開くことができます。 といっても公式ページトップの"ACCOUNT"メニューの"Sing in"を開いたのと同じなんだけどね。  アカウント登録時に登録したユーザーID(メールアドレス)とパスワードを入力して"LOGIN"をクリックすればログインした状態の公式ページが表示されます。  (4) VILABS公式サイトからUVI Workstation をダウンロード&インストールする(他にVILABが対応するDAWソフトがインストールされていなければ使用するのに必須) UVI workstationは、公式のインストーラを使用すればその中で自動的にダウンロードされインストールされますが、公式のインストーラをダウンロードするのに超時間がかかる(サーバー側で帯域制限がかかったいると思われる)ので、UVI workstationを直サイトからダウンロードしてインストールします。 公式サイトの"SUPPORT"メニューから"UVI workstation"を選択します。  UVI workstationページが表示されたら、使用するPC(Apple もしくは Windows 64bit)のいずれかのダウンロードリンクをクリックしてダウンロードします。  ダウンロードされたイメージを実行するとインストールします。 (5) VILABS公式サイトで購入業者からメールで送られてくる製品シリアル番号を登録する VILABS公式ページにログインすると開けるようになる、"Authorize"ページを開いて、製品シリアル番号の登録を行います。  この際に予め先ほどのiLOK公式サイトで自分のアカウントでログインしておく必要があります。  ここで予めログインしてあるiLOKのユーザーIDを確認用も含めて同じものを入力して、代理店から送られてきた製品シリアル番号をコピー&ペーストして、"AUTHRIZE"ボタンをクリックすれば製品登録完了。  この際にiLOK公式サイト上でもライセンスキーが生成され、最大3つまでのPC上でACTIVATEして利用できるようになります。  この段階ではまだ、activateされたライセンス数は0なので、使用するPC上のiLOK license managerでPC上でライセンスをactivateする必要があります。 (6) iLOK license manager を起動して、iLOK singin ボタンをクリックして自分のiLOK アカウントのユーザ名とパスワードを入力してログインする  ライセンスを選択すると詳しいライセンス情報が表示されます。  これで最大3つのPCにインストールして使用できるライセンスが登録済であることが確認できます。 次にPC上で製品を利用できるようにactivateを行う必要があります。 (7) iLOK licence managerで表示されるVILABSで登録した製品シリアル番号を現在のPC上でactivateする(ひとつの製品は同時期に3つのPC上でactivate可能、リアルタイム演奏用、DAWデスクトップPC用、屋外演奏用ノートPC等で同時使用が考慮されている) iLOK license managerで続けて、ライセンス行で右クリックするしてactivateメニューを選択するとそのライセンスを現在のPCでactivateするための画面が表示されます。  "Activate"ボタンをクリックするだけ。  (8) VILABS公式サイトで登録したアカウントでログインし、Ravenscroft 275 ライブラリをダウンロードする 以降VILABS公式ページにログインして"Downloads/Serial"ページを開くと、VILAB謹製のインストーラ(なくてもインストールはできる)や、製品のダウンロードができるページが表示されます。  Apple用とWindows用にそれぞれ公式のインストーラが用意されていますが、製品導入に必要なステップを順番にガイドするだけなので、それを使用しなくても手順が判っていれば必須ではないです。また不要な手順とかもあったりするので誤解を招く恐れがあります。 ダウンロードリンクをクリックするとブラウザーによってデフォルトのダウンロードディレクトリにRARで圧縮された製品がダウンロードされます。 製品を使用する前にUVI Workstationを予め導入しておく必要があります。 (9) ダウンロードしたライブラリは圧縮されているので、解凍ソフト(RAR)を別途ダウンロード&インストールする ダウンロードされたRARファイルは、別途RARをダウンロードしてインストールして解凍する必要がありますが、解凍先はUVI workstationのsoundbankディレクトリを指定するのが良いです。 (10) Ravenscroft 275 ライブラリを解凍して、UVI workstationのsoundbankディレクトリに展開する(場所はどこでもいいが、それ以外の場所だとUVI workstationで設定をそちらに変更する必要がある) SSDとかが別途搭載されたPCの場合には、SSDドライブ上のフォルダーに展開すべきかもしれません。その場合にはUVI workstationの設定でそちらから背品をロードするように変更する必要があります。 (11) UVI workstationを起動して、展開されたRavenscroft 275音源をロードする soundbankにダウンロードした製品を解凍してもまだ UVI workstation上では使用できません。 UVI workstationではsoundbankの中から音源ソフトをひとつ選択してロードする必要があります。  あともう少しです。 一番上に表示されている、"Double-clink to open browser"をクリックすると、ロード可能な音源一覧が出てくるので、そこからRavenscroft 275を選択すると、ロード画面が表示されます。  ロードが完了すると、良く見かけるravenscroft 275のplugin画面が表示されます。  さて、これであとは動作確認するだけなんだけど、それにはまだやることがあります。 (12) PCにMIDIキーボードを接続後にUVI workstationのFileメニューにあるAudio and MIDI settingメニューを開いて、MIDI settingを開いて、MIDI device rescanボタンを押して、A portのデバイス選択をクリックして認識されているMIDI keyboardを選択する 予めリアルタイム演奏に使用するMIDIキーボード(ここではYAMAHA P115B)をPCにUSBで接続して電源を入れておきます。 UVI workstationの唯一のメニューである"Audio and MIDI settings"を開いて、MIDI settingsタブを選択します。 そこで"Refresh MIDI devices"をクリックして現在PCで使用可能なMIDIデバイスをスキャンさせます。 PORT AのMIDI INPUT欄をクリックすると、選択肢の中に使用可能なMIDIデバイス名が出てくるのでそれを選択します。 これだけでリアルタイム演奏ができるようになります。 ここまでやるのも説明するのも大変だった( ´Д`) せっかくだから、Ravenscroft 275 PC音源のさわりを説明。 音源をロード後表示される、歯車のアイコンをクリックすると、良く見かけるRavenscroft 275音源の設定画面が表示されます。  この画面で大部分の音源設定が行えます。 デフォルトのマイクセッティングはCLOSEで、ピアノの響板の真上にマイクをセッティングした状態を再現しています。 それ以外に CLOSE, PLAYER, ROOM, SIDEそれぞれをデフォルトのマイクセッティングにした音源がブラウザーメニューから選択できますが、設定画面のマイクミキシング設定を変更しても同じことが可能です。 iOS用のUVI Ravenscroft 275 pianoではできない複数のマイクセッティングからのミキシングが可能です(かなりプロ仕様)。 たしかにそれぞれのマイクセッティングで試し引きするとそれらしき音色の違いや響き、音域のバランスの違いが明白です。 設定画面中央下部にあるのが、MIDI上でのペダル設定とベロシティのマッピングとダイナミックレンジ設定。 ウナコルダペダルはデフォルトでは効かないので、有効にしてみると、確かに弱音効果があることがわかります。ハンマーが叩かなくなった弦が共鳴しているかどうかは謎。 ハーフペダルを有効にすると、段階的なペダルレゾナンス効果があるようです。でもデジタル的なのであることろからレゾナンスし始めるというのがはっきりわかります。まあ、これは再現が見つかしいよね。過剰な期待は禁物。 ベロシティマッピングは歯車アイコンの右隣りにある階段状のアイコンをクリックすると細かなキャリブレーション設定が可能ですが、iOS版のほうが簡易だけど、設定しやすい気がする。 設定画面の左側は、キーリリース音、ペダル音、打鍵音などの下部ノイズの再現度の設定、同音連打、無音打鍵とかマニアックな設定も可能(使うの?)。 設定画面の右側は、各種共鳴に関する設定、"TRUE PEDAL ACTION"とか"REPEDAL"は専門的すぎて理解不能。リバーブもデフォルトではオフですが、設定可能。 設定画面の歯車の横のアイコンを開くとベロシティマッピングを細かく設定できる画面が開きます。  ここでベロシティの各レベルに対して音量を対応させることができますが、面倒( ´Д`) MODARTT PIANOTEQみたいにキャリブレーション機能とか欲しいところだよね。 この画面を使うと、使用しているMIDIキーボードを使用してキーを打鍵した際のベロシティの最小値と最大値がわかるので、それに基づいてカーブを設定するといいかもね。 ちなみに手元のYAMAHA P115Bでは、最大でも90ぐらいしか出ないので、PIANOTEQでキャリブレーションするとFF以降が90ぐらいで頭打ちになり、それまでは0からリニアーなカーブになるのでした。 ベロシティ設定アイコンの隣の音叉のアイコンをクリックすると音律設定画面が開きます。 おお、音律を変えられるのか、とPIANOTEQ Standard版のような期待を抱いたのが間違いでした( ´Д`)  デフォルトは平均律("equal temperament")で、それ以外に設定可能なのが、純正律("Just")、ピタゴラス音律("pythagore Major/Minor")、と任意("Modified")だけ。 PIANOTEQの音律の設定を参考に、CENTSを割り振って任意の音律にすることは可能だけど、調律師レベルの知識が必要で素人には難しいね(;´Д`) もうここまでくるのが大変だったので、音出しでいろいろ試したかったけど、音色は好きなRavenscroft 275のそれなので一安心。 PC用のRavenscroft 275音源はpluginとしてしか提供されていないので、他の市販の機能豊富なDAWソフトで使えば録音とかオーディオファイルへのレンダリングとかできるだろうけど、UVI workstationでそれをやるには、まずMIDIファイルを取り込んで音源にルーティングするpluginが別に必要だし、音源の出力をファイルに書き出すpluginも必要。 PIANOTEQ みたいにスタンドアロンで録音もオーディオファイルへのレンダリングもできるようには気が利いていないんだよね。 それと音源のプリセットもマイクセッティング別を除いては用意されていないから、自分で用途と好みにかわせて設定しないといけないんだよね。iOS版のRavenscroft 275 pianoは予めイコライザーやリバーブとかのエフェクトの方法なプリセットがあるので、それをベースに好みに変更すればよかったのとは大違い。 それが確認できただけでも収穫かな。 お疲れ様(;´Д`) やっとご飯たべれる |
| webadm | 投稿日時: 2020-6-4 13:14 |
Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3110 |
Re: VILAB Ravenscroft 275 PC音源購入 先般ご紹介した、VILAB Ravenscroft 275の続きがあります。
UVI workstationをスタンドアロンプレイヤーとしてリアルタイム演奏ができるようになったので、練習の仕上げとかで使っています。 ただPIANOTEQみたいにMIDIキャプチャ(録音)とかできないのが不満でした。 通しで演奏したら録音して再生してチェックしたいけどそれがUVI Workstationではできないようです。 それとインストールした直後は詳細を調べてなかったのですが、アンビニエンスエフェクター(ディレイとリバーブ)に関してはいくつものプリセットが用意されていて選択すればそれぽい響きが得られることが判明しました。  録音するには、Garagebandのように録音機能が元々備わっているDAWの上でpluginとしてVILAB Ravenscroft 275音源を使用する必要があります。 PC用の市販のDAWソフトウェアでVST pluginやAU pluginに対応したものであれば、VILAB Ravenscroft 275音源を使うことができます。 手元のwindowsノートPCにはCakewalkという無料で使える良くできたDAWをインストールしたまま使ってなかったので、試してみることにしました。 そしたら前に入れたPIANOTEQはpluginのリストに出てくるものの、VILAB Ravenscroft 275が出てきません。 どうやら、考え違いをしていたらしく、UVI Workstationを導入した時に、オプションでVST pluginとして登録するチェックボックスを変更して登録しないようにしてインストールしたのが敗因でした。 VILABが出している各種音源はいずれもUVI Workstation内にロードして使う形式になっており、それ自身は標準的なplugin形式ではなく、独自の形式でした。VST pluginとして利用可能なのは、UVI Workstationそのものだったのです。 つまり、UVI WorkstationはVST pluginの仕様を満たした貝殻(シェル)みたいなもので、VILABの音源製品はその貝殻の中に住まうヤドカリみたいな存在だったわけです。 なので、ちょいと新しいUVI Workstationのバージョンをダウンロードしてインストールしなおすことに。今度はVSTのチェックボックスはそのままにしてインストールしました。 そしたら今度はCakewalkでpluginリストにUVI Workstationが表れました。  こんなことどこに書いてないじゃん( ´Д`) わかりずれー(´Д` ) 追加したトラックにplugin音源としてUVI Workstationを選択すると、自動的にplugin(UVI Workstaion)が起動されpluginとしてのUVI Workstaionウインドウが表示されます。  あとはUVI Workstation上にravenscroft 275音源をロードすればいいだけ。 で初めてCakewalkを使ってリアルタイム演奏の録音と再生を試してみました。 DAWの使い方は仕組みが想像つくのでなんとなく設定すればできたけど、素人には難しいかもね。 基本はMIDI入力が接続したUSB MIDIキーボード(今回はYAMAHA P-115B)のMIDIデバイス設定画面に候補として現れているのをチェックボックスをチェックして保存するだけなんだけどね。 Cakewalkの場合、候補リストに無いMIDIデバイスを検出すると候補リストに追加するか確認を求めるので、そこでOKすれば候補リストに追加されるけど、選択は別途行う必要がありました。  これらの設定をしたDAW プロジェクトは保存しておけば保存時の状態が開くだけで復元されるので、UVI Workstation上には保存機能はないのでした。 DAWの録音機能は、ソフトによって仕様は異なるでしょうが、Cakewlakの場合、トラック毎に録音するかどうかの設定があり、全体として録音開始ボタンがあって、録音が有効なトラックに関してのみ録音が始まるという仕組みのようです。 試してみると、うまくいきました。 録音時にCakewalkに内蔵されたメトロノームがデフォルトで有効みたいで、結構本物のメトロノームと同じ音がして良い感じでした。 でも結構大げさだよね。 DAWの場合は、MIDI録音はリアルタイムで録音しっぱなしという方法と、ステップ録音というのがあり、それを使うと楽譜を見ながら一音一音入れていくことができます。後で編集で音価とかベロシティー(強弱)を変更できるので、いわゆる打ち込み用ですね。 でももっと簡単なデジタルピアノ的な録音再生機能がいいんだけどね。 そう考えるとデジタルピアノの録音再生機能は便利だよね。 DAWだとPC立ち上げて音出せるまで手間がかかるし、録音再生もボタン押すだけとはいえ、マウスかポインティングデバイス操作が必要だし。 そんなこんなでデジタルピアノの使いやすさを再認識したのでした。 あと、リアルタイム演奏を試して気づいたのが、デジタルピアノと一緒に買った同じYAMAHAのオープンエア式のヘッドフォンはいいんだけど、昔買ったちょっと値が張ったAudiotechnicaの密閉式ヘッドフォンの調子が悪いのに気づきました。 デジタルピアノのヘッドフォンはそのデジタルピアノのメーカー製のヘッドフォンがお勧めです。 というのも、ヘッドフォン端子の回路とかはメーカーによって異なるし、インピーダンスもスピーカーと違って標準というのが無いのでインピーダンスが異なる同士をつなげると周波数特性が変わってしまって本来の性能が出ないためです。 同じメーカーならその会社内の標準でインピーダンスは統一されているはずなので、相性はいいはず。 それとオープンエアタイプがお勧め。というのも長い時間耳を塞ぐので、密閉式だと耳の内部から体の外に出てくる水蒸気の逃げ場が無くなるので、耳の中の湿度が上昇し耳の中の環境に良くないためです。カビが生えたり感染症を起こす可能性があります。 特にお風呂入ってからちょっと練習という時には密閉型は禁物です。 あと小型のイヤフォンは低い周波数の音量が小さくなるので、バスとかが実際より小さく聞こえるので音のバランスが良くないです。 なのでできれば周波数特性が平坦なスタジオモニター用ヘッドフォンが理想的ですが、デジタルピアノメーカーの出しているヘッドフォンで十分かな。 密閉型で金属部品を使っているものは、耳から出る水蒸気で密閉型ならなおさら湿気に晒されるため、今回のAudiotechnicaのヘッドフォンみたいに、使っているうち周波数特性が変わってしまって聞くに堪えない音しか鳴らなくなってしまう事態が発生します。 しばらく一日放置すると解消するんだけど、もう我慢ならないよね。 今度評判の良いスタディオモニター用ヘッドフォンを試してみる予定(オープンエアタイプね)。 あと、ノートPC内蔵のサウンドチップだとスペック不足なのか、高調波ノイズ(高音だとキンキン鳴る)が気になるので、スペックの高いUSB DACを使うべきなのかも。もしくはハイレゾ対応USB ヘッドフォンアンプとかね。 んじゃまた。 |
| webadm | 投稿日時: 2020-6-14 7:48 |
Webmaster   登録日: 2004-11-7 居住地: 投稿: 3110 |
オーディオファイル出力 これまでRavenscroft 275音源での演奏をオーディオファイルに落とすために以下の方法を使っていました。
・iOS上のUVI Ravenscroft 275 PianoアプリをGaragebandの外部音源としたトラックを作成し、そこにリアルタイム演奏をキャプチャしたMIDIデータファイルをドラッグ&ドロップして再生し、iPadのヘッドフォン出力からWalkmanで録音 この方法だとヘッドフォン出力からWalkmanの録音入力までの間はアナログオーディオ信号になるため、ノイズの混入や不適切なオーディオレベル、音の劣化が伴う可能性がありました。 それとPIANOTEQのように直接オーディオファイルに出力できるのと比べて、沢山手間がかかるというのが一番の難点でした。 今回PC用のVILAB Ravenscroft 275を購入して、フリーのDAWであるCakewalkで使えるようになったので、DAWが備えているオーディオファイル作成機能を使用すればPIANOTEQと同様にPC上だけでオールデジタル処理で完結することになります。 まず最初に、予めUVI Ravenscroft 275プラグイン(UVI Workstation)をinstrumentとしたトラックを追加して保存したプロジェクトを開きます。 次にトラックを選択して右クリックメニューを開きます。  するとメニューの中に"MIDIのインポート(MI..."というエントリがあるので、それを選択します。  ファイル選択ダイアログが出るので、予め用意したMIDIデータファイルを選択して"開く"をクリックします。  すると全部で16のMIDIトラックが新たに追加され、追加された最初のMIDIトラックにインポートしたMIDIファイルのピアノロール表示があることを確認できます。  この状態ではMIDIトラックの出力はデフォルトのMIDI出力デバイスになっているため、Ravenscroft 275プラグインを使用してデジタルオーディオ出力を得るために、出力先をUVI Workstationに変更する必要があります。  出力先を確認すると、プロジェクトに設定されたMIDI 出力デバイス名が表示されます。 出力先をクリックして、出力先リストから、"UVI Workstation"を選択します。  上のスクリーンショットでは、その前に試したPIANOTEQを使用したプロジェクトのものなので、PIANOTEQを選択していますが、VILABの場合は、UVI Workstationが選択リストにあるのでそれを選択します。 それがすんだら、再生ボタンをクリックしてちゃんと演奏が再生されることを確認します。  そしていよいよ、オーディオファイル出力です。 Cakewalkの場合は、右上に"エクスポート"ボタンがあるので、それをクリックしてエクスポートメニューを表示させます。  エクスポートメニューの中からオーディオを選択すると、オーディオフォーマットサブメニューが表れます。  その中から、ロスレス圧縮ならFLACを、ロスあり圧縮ならMP3を選択すると、ファイル保存ダイアログが現れるので、出力ファイル名や出力ファイルのフォルダーを設定します。  "保存"ボタンをクリックすると、今度はオーディオフォーマットに依存した設定ダイアログが現れるので、変更の必要があれば変更して"OK"ボタンをクリックするとレンダリングが開始します。  上のスクリーンショットでは、MP3のビットレートを192Kに変更して高品質にしています。 Mp3はビットレートを上げると情報量が増える代わりにサイズが大きくなります。 WAVとか非圧縮フォーマットもありますが、ファイルサイズが大きくなるので、それが必要な目的以外は圧縮フォーマットを使用するのが良いです。FLACならWAVと同じ情報を損なわずに圧縮しているので、WAVよりもサイズは小さいですが、それでもMP3に比べると巨大になります。 あとは、設定した出力先フォルダーに指定したファイル名のオーディオファイルが出来ているのを確認し、PC上のオーディオプレイヤーで再生して確認するだけです。 んじゃまた。 |
| スレッド表示 | 新しいものから | 前のトピック | 次のトピック | トップ |